
写真1:秋光教授

写真2:左から銭谷・中川・永松・広中氏
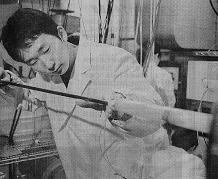
写真3:実験中の永松氏(日本経済新聞2001年4月4日夕刊より)
一方、日本物理学会(中央大学多摩キャンパス)でも3月29日夜に異例の「インフォーマルシンポジウム」が開催され、プレス発表の後、やはり秋光教授の招待講演に続いて27件の研究成果が、会場の使用期限ぎりぎりの午後10時まで発表された。2週間の時間遅れもあるが、よりレベルの高い発表が多かったという。4月17日からの米国MRS春季年会でも特別セッションが予定されている。
なお、5月24日(木)には超伝導科学技術フォーラム(未踏科学技術協会:03-3503-4681)のシンポジウムが青山学院大学青山キャンパス国際会議室で行われ、秋光教授の「高温超伝導の夢を追って」と題される講演が10時よりある。教授は、普段は口が固いが、酒席になると「今回の発表は実はまだ松竹梅の梅。まもなく、竹と松を発表できるようになりますよ。」と周囲に気をもたせているという。
金属材料技術研究所第1研究グループ戸叶一正総合研究官は「1月10日、仙台での秋光先生の発表後、大変な発見だと思ってその日から追試を開始した。アメリカでも立ち上がりの早かったのはエイムス研究所やウィスコンシン大学など、かつて金属系の超伝導体で活躍したグループである。臨界温度が40 Kということは従来の実用金属系線材に比べて冷却が楽になり実用的な意義も大きい。A15型化合物と同様に硬くて塑性加工が不可能な問題はあるが、ブロンズ法のようなブレークスルーが必ず生み出されると思う。」と語っている。
秋光教授とともに新物質探索で著名なプリンストン大学(前ベル研究所) Robert J. Cava教授はNature3月1日号で以下のようにこのニュースへの印象を伝えている。「MgB2が39 Kで超伝導になるという秋光らのグループの発表に、超伝導界は大きな衝撃を受けた。過去15年間、超伝導関係者は酸化物超伝導体の研究に熱中し、その転移温度の低さから金属超伝導体の研究はあまり注目を集めていなかった。秋光は今年1月に仙台で開催された会議でMgB2の超伝導をはじめて発表したようだが、私がこの情報を入手したのは数週間後であった。それも複雑な経路をたどったe-mailや口伝えであった。本当であれば大変喜ばしく、その反面真偽が明らかでない情報が世界へと伝達されていくプロセスはまさに15年前の酸化物超伝導体の発見と似ていた。(中略)秋光らの発見は、過去にホウ化物超伝導体に対して予測されたことを証明する結果となった。つまり、軽元素であるホウ素は格子振動の振動数が大きく、転移温度が高くなるというものである。現在までホウ化物超伝導体は存在したが、この仮説を裏付ける結果は得られていなかった。仮にMgB2が1960から70年代に発見されていたら、超伝導の研究は全く異なった方向へ向いていたであろう。当時活躍していた研究者はホウ化物で超伝導体を探索していたが、MgB2は発見できなかった。よって酸化物超伝導体が発見されるまでの数十年間、30 Kを超える転移温度を持つ超伝導体は存在しないと諦められていた。この発見が材料物理に与える影響を評価するには、MgB2だけが高温で超伝導になるのか、それともMgB2は氷山の一角に過ぎないのかで決まるであろう。酸化物超伝導では氷山の底を未だに見ることができていない。MgB2の氷山の底も同じ位深いことを期待している。)
一方、このようなフィーバーが出現した原因を東京大学北澤宏一教授は以下のように分析している。
1)秋光教授らのボライド系での発見は、23 K(従来金属の最高のTc)を越す近年に見出された5つの新超伝導体(前号記載)と併せて考えると非常に興味深い。周期律表の最も軽い元素群のうち、連なった4元素、B、C、N、Oで高温超伝導が発現している―という見方も可能になる。いずれもイオン結合と共有結合とを空間的に分離した形で持っていることが特徴で、新たな高温超伝導探索のための鉱脈が現われたと感じている人たちがいること。
2)これまで銅酸化物高温超伝導に対して築き上げられてきたメカニズムの考え方(複数あるが)が、再び理論的混沌(高温超伝導発見時代に起こった)時代を迎えて欲しいとする期待。あるいは、さらに異なった新超伝導機構が現われたのではないかとする期待。今回の物質が、仮にBCSフォノン機構とすると、従来、囁かれていた「BCSの壁」がなぜ乗り越えられたのかが理論的に解明されねばならない。1986年以前、理論家たちは23 Kを超えない超伝導に対して、それは「BCSの壁」のせいであると説明して、物質探索家たちを落胆させていた。銅酸化物が発見されてしまうと、「それは違うメカニズムが現われたのだからTcが高くなって当然」とした。
もしも、今回の物質において、高いエネルギーをもつフォノンがうまく電子とカプルしているのだとしたら、「どのような物質ではそれがうまくいくのか」を予言する責任があろう。「理論は新物質開発になんの役にも立ったことがない」という故B. T. Matthiasの言葉を跳ね返すチャンスだろう。
MgB2ではボロン層内での伸縮振動モードの周波数の高いフォノン(ラマン活性との見方がある)の関与が取りざたされているが、すでに23Kを越す非酸化銅系超伝導体は5つも発見されてきている。
3)今回のMgB2そのものでも、冷凍機直冷が容易な20 Kという温度で実用材料になる可能性があること。銅酸化物系と異なり、線材として弱結合がシリアスな問題とならない利点を持つことがすでに指摘された。Mgリッチ組成で線材加工ができる可能性。マトリックス金属の制約が少ない点(銅酸化物では高価な銀が必須)。入手可能なボロンファイバーを基本にした線材製造法の可能性。MgやBのMOCVD試薬は入手容易、等々の利点が言われているが、使用温度の20 Kで臨界磁場Hc2が10 Tを切る点が「性能として中途半端」という声も聞かれる。今後、不純物添加などで電子の平均自由行程を短くし、Hc2向上を図れるかどうか、あるいは、さらにその周辺により高性能の新相が現われるかどうかによって、今後のインパクトの大きさが決まりそうだ。また、たとえ20Kでの使用が上限としても、将来的にヘリウム温度での使用が行われないとは限らないので、金属超伝導線材の市場にとってもウォッチングは必要。一方、電子素子応用はMgB2そのものでも大きなインパクトがありうる。IcRn積が大きく、また、コヒーレンス長が使いやすい長さらしいこと。薄膜の製造が容易。ただし、ジャンクションが作り易いかは未知。s波超伝導と思われるので、接合特性はd波の銅酸化物系に比較してシャープな特性が期待できる。
4)14年前に発見された高温超伝導を含めて、冷却技術と地味な技術開発努力の継続の中で実用化に向けた超伝導技術があちこちで夜明け前の段階に達してきている(北澤:応用物理誌2001年1月号総合報告に解説)。閉塞感の強い時代に、環境に対応できる新技術への待望論が高まっていること。このような時期に、秋光研の発見が報じられたことは象徴的、としている。
本稿では、以下、米国物理学会、日本物理学会での発表を中心に、MgB2をめぐる情報をお伝えする。
●関連する新物質
両学会での本系に関連した新超伝導体発見の報告は、秋光グループ自身によるBの一部をBeで置換したMgBxBe2-x(x〜1.3、Tc=35 K)のみであった。組成の詳細などはまだ良くわかっていない。中国科学院北京物理学研究所によりWeb上で公開されて話題を呼んだ(Mg,Cu)B2(Tc=47 K)は、数日後「著者の一部の発表同意を得ていない」という理由により取り下げられ、米国物理学会でも同グループによる発表はなかった。また、この系は金材研の戸叶グループによっても探索されたが、Cuの添加によりTcは下がっていくとされている。
その他の置換効果としては、MgのAl置換、BのC置換効果(いずれも電子ドープに対応する)が北陸先端大の竹延等によって報告されたが、Tcはドープとともに単調に減少する。また、ISTEC-SRLの山本等はMgを様々な金属で置換することを試みたが、Zn、Au、Agなどはほとんど固溶しないと報告し、むしろ、これらの金属をピン止め中心や線材化する際の助剤として積極的に使えるのではないかとコメントした。
一方B系ではないが、Mgを含む新しい超伝導体としてプリンストン大学のCavaグループからペロブスカイト型の構造を持つMgCNi3(Tc=8 K)が発表された。
●材料としての製造方式
MgB2の試料作製に関しては、バルク、薄膜、線材など多くの発表があった。しかしながら、物性測定の立場から最も要求の高い単結晶の合成に成功したという報告は残念ながら一件もなかった。
バルク材に関して、金材研の高野等は市販のMgB2粉末を3.5GPaの高圧下で1000℃2時間焼結することによって、ほぼ理論密度に匹敵する高密度のバルク試料を得られると発表した。東大工学部の為ヶ井等は、この試料を用いたMO測定から、試料全体で臨界状態が形成されていることを報告した。ウィスコンシン大グループはMgB2では銅酸化物で見られる粒界弱結合(粒境界で臨界電流が弱まる現象)の問題が軽減されているように見受けられると報告している。また、筑波大の古山等は高圧をかけなくても、1100℃という比較的高い温度で24時間焼結することによって高密度試料が得られるとしている。
線材に向けた努力としては、市販されているボロンファイバー(太さ100μm)を使って、それにMgガスを吸収させる形で作製された長さ5 cmの試料が、薄膜に匹敵する程度の臨界電流を与えていることが注目される(エイムス研究所)。ただし、MgB2のHc2は絶対零度でも12〜18T程度と報告されており(エイムス研究所、金材研など)、銅酸化物に対してMgB2そのものが線材としての魅力を出せるかどうかについては予断を許さない。また、液体窒素温度でのケーブルなどの応用はTcの高い物質が発見されるのを待たねばならない。この点、すでに銅酸化物は液体窒素温度でも4万A/cm2を超えるものが出てきている。したがって、実用線材としての期待は、20 K以下での磁場下臨界電流特性が相対的に銅酸化物を上回ることができるかどうか、また、クエンチ特性などに注目すべきであろう。このようなデータは、当然のことではあるが、まだ報告されていない。
一方、本物質で比較的すぐに有望と考えられるデバイス応用に不可欠な薄膜に関しては、パルスレーザーデポジション法によって作製された薄膜が、銅酸化物系に対して遜色のない100万A/cm2以上の臨界電流を液体ヘリウム温度で持つことが注目される(ウィスコンシン大、ポハン科技大)。MgB2の薄膜は銅酸化物より作り易いとされる。MgB2は10〜20 Kでの使用が期待出来るため、小型超伝導素子としての応用を考えた場合、冷凍機の負荷が液体He温度に比較して数倍から10数倍も軽くなるという有利な条件を備えている。あるいは、液体He温度に冷却したとすれば、従来材料に比較してシャープな特性とより大きなIcRn接合特性が期待できる。Hc2が低いことは磁場中応用には不利であるがコヒーレンス長が長いことを意味し、コヒーレンス長が極端に短い銅酸化物系に較べて、エレクトロニクス応用は急速な展開をみる可能性がある。
●MgB2の物性に関する報告
両学会でのほとんどの発表は、MgB2そのものの物性の報告が中心であった。興味の中心は、この新超伝導体が旧来のBCS理論の延長として理解できるものであるかどうかにある。以下、各項目別にトピックスを紹介したい。
バンド構造:電子状態を知る上での基礎となるバンド計算は、最近の結果と多少の違いはあるものの、1970年代に既にソ連(当時)や英国で行われていた。今回の両学会では米国海軍研、カリフォルニア大デービス校、阪大産研などから新しいバンド計算の報告があった。計算結果によるとMgB2のMgはほぼイオン化しており(Mg2+)、ハニカム状に並んだB1個あたり1個の電子を供給する。したがって、B面の電子数は、Bより電子の一つ多いCから成るグラファイトと同じであり、MgB2のバンド構造はグラファイトと対応付けて考えることができる。フェルミ面近傍の電子状態は、sp2軌道から構成されるpsバンドとpz軌道から構成されるppバンドから成っている。グラファイトではpsバンドの位置が深く、全て電子で埋められているのに対し、MgB2では、psバンドがフェルミ面にかかっており、2次元的なシリンダー状のホールのフェルミ面を形成しているのが特徴である。ppバンドは3次元的なネットワーク状のフェルミ面(電子面とホール面)を形成しているが、psバンドのホールのためにppバンドに電子が供給され、電子面はホール面にくらべて肥大している。Mgはフェルミ面での状態にほとんど寄与しない。
これらのフェルミ面やバンド構造を確認する実験はまだほとんど行われていない。フロリダ強磁場研は、配向試料でドハースファンアルフェン効果を観測したと発表したが、観測されたフェルミ面の断面積や、どのブランチを観測しているか等の報告はなかった。物構研放射光のグループは共鳴光電子分光の実験からBの内殻のバンドが全体的にバンド計算より深くなっていると報告している。バンド構造の詳しい検証は、単結晶を用いた精密な実験を待つ必要があると思われる。
同位体効果:狭義のBCSの電子対形成機構であるフォノン機構を示唆する上で、最も有力な証拠となる同位体効果の実験は、本物質の発表直後にエイムス研究所でBに対して行われ、10Bを11Bで置換するとTcが約1K低下することが報告された。これはTc∝M-aと書いた場合のaB〜0.26に相当し、BCSから期待される0.5よりは小さいが、フォノンが何らかの形で超伝導に関係していることは間違いない。一方アルゴンヌ国立研のグループは、Bの場合とは異なりMgの同位体効果がほとんど無い(aMg〜0.02)ことを報告した。
電子格子相互作用:電子格子相互作用に関しては、格子変形を取り入れたバンド計算、フォノン分散や状態密度の計算による理論的アプローチの他、中性子非弾性散乱によるフォノン状態密度測定の実験結果が発表された。米国海軍研、カリフォルニア大デービス校、NIST等のグループは、バンド計算から、G点でE2g対称を持つB面内の光学フォノンがMgB2の特徴であるpsバンドと強く結合すると報告している。計算から求められている電子フォノン結合定数lは約1であり、やや強結合の領域にある。フォノン分散の計算から見積もられるE2gフォノンのエネルギーは60 meV程度以上と高く、また、このフォノンは非調和性が強いことが計算から示されており、これらが高いTcの原因であるという見方がある。これらの結果はBのみで同位体効果が存在することとコンシステントである。
中性子非弾性散乱の結果は青山学院大、金材研、アルゴンヌ国立研等のグループから報告された。測定されたフォノン状態密度は計算とおおよそ一致している。青山学院大のグループは、Tc以下で24 meVにあるフォノンのGDOSのピークが増大し、80〜100 meVにあるピークは逆に減少すると報告した。実際にどのフォノンモードが変化していのるかを特定するには、データの統計性の問題など、まだ微妙な点があるようである。
超伝導ギャップ:超伝導ギャップの対称性に関しては、Hc1の温度依存性(中国科学院北京物理学研)や磁場侵入長の温度依存性(中国科学院北京物理学研、ケンブリッジ大)から非s波的ペアリングを主張するグループもあるが、多くの測定結果はs波的な等方的ギャップを示唆している。阪大基礎工の石田等はNMRのスピン格子緩和率T1-1の測定を行い、Tc以下でT1-1が指数関数的に減少すること、Tc直下に弱いながらもコヒーレンスピーク(約1.2倍の増大)が存在することを報告し、s波を主張した。T1-1の温度依存性から見積もられた2D/kBTcは約5と大きく、この結果からは非常に強結合領域にあることになる。また、室温までコリンハ則が成り立ち、スピン揺らぎの影響は見られていない。都立大のグループは、スピン1重項ペアリングを示唆するTc以下でのナイトシフトの減少(s波と無矛盾)を報告した。
広島大、アルゴンヌ国立研などのグループはブレークジャンクションや点接触によるトンネルスペクトルの報告を行った。2D/kBTcの値が弱結合の場合のユニバーサルな値の3.5より小さいという異常なギャップから、NMRで見られるような2D/kBTc〜5のギャップまでが報告され、データはまだ収束していないが、小さいギャップの方が再現性が良く、ギャップ端の準粒子ピーク構造も鋭いようである。
東北大理学部の高橋グループ、東大物性研の辛グループは超高分解能光電子分光の結果を報告した。ギャップの大きさはやはり弱結合で期待される値より小さい。辛グループはさらに、光電子スペクトルにフォノン構造を観測したと発表した。
トンネル分光、光電子分光は表面敏感な手法であり、たとえ超高真空中で準備された表面でも、焼結体では粒界の影響などが考えられるため、真の清浄表面を観測しているかどうかは検討が必要であろう。単結晶を用いた実験が待たれる。また、辛グループは光電子分光から、ジュネーブ大グループは比熱の測定結果からギャップ内に構造があると報告している。ギャップの大きさや詳細な構造、異方性の解明が今後の実験研究の焦点である。
熱測定、輸送特性など:ローレンスバークレー国立研、ETH、エイムス研、ジュネーブ大等のグループが比熱の測定結果を報告している。電子比熱係数は3 mJ/mol K2程度であり、バンド計算から期待される値の倍程度となっている。これがフォノンの効果であるとすると、電子フォノン結合定数はl〜1となり、電子フォノン相互作用の計算結果と同程度である。また、比熱の磁場依存性は、等方的s波の磁束芯から期待される磁場に比例した振る舞いから逸脱して磁場のsub-linearになっている。
ヒューストン大のChuグループは熱電能の温度依存性の測定結果を報告した。熱電能は正で、150 K以下では温度に比例する金属的な振る舞いを示す。また、プリンストン大のOngグループはホール効果の測定を行い、ホール係数は熱電能同様正であることを報告した。
格子定数やTcに対する圧力効果は非常に多くのグループから報告されている。結果はグループによって数値に多小の違いはあるものの、c軸がa軸より縮みやすく、dTc/dPは負で-1〜-2K/GPaの値をとる点では一致している。
超伝導発現機構:超伝導ギャップをめぐる実験がほぼs波を示唆していること、電子格子相互作用の計算からは、高エネルギーフォノンとBのpsバンドのカップリングによって高いTc が矛盾無く説明されることから、MgB2の超伝導はBCS強結合理論の枠組みで理解できるという見方が大勢を占めているようである。しかし、いくつかの新しい超伝導発現機構がMgB2の発見を契機に提案されている。この様な新機構の提案は、米国物理学会では80件近い講演の中で1つのグループ(カリフォルニア大サンディエゴ校のHirsch等)からしかなかったのに対し、日本物理学会では物性研の今田、阪大基礎工の河野等、青山学院大の古川、電総研の山地等、など複数のグループから提案があったことは、両学会間に二週間の差があったことを考慮しても注目に値する。実際、ウェブ速報cond-matにも欧米で加州大サンディエゴのHirsch以外のグループからの新機構提案のプレプリントは無いようである。(3月30日現在)
Hirsch等はpsバンドにホールが少量あることが本質的で、これらのホールが対を形成することで運動エネルギーを稼ぐとしている。今田はフェルミ面を横切るpsバンドとppバンド間のクーロン相互作用が重要であると指摘した。このモデルではpsバンドのギャップはppバンドのギャップより数倍大きく、また、二つのバンドでギャップの位相が逆になるという特徴を持つという。河野等はpsバンドを二次元電子ガスと見なし、そこにクーロン相互作用を取り入れた時の超伝導発現を論じた。古川はppバンドがhalf fillingにあるときに有限の層間ホッピングがあるとkz方向に完全なネスティングが起こることを指摘し、MgB2は反強磁性SDWの揺らぎが強い系であるとしている。また、ネスティングベクトル方向に伸びているpsバンドのフェルミ面は、この反強磁性揺らぎと結合する可能性があるという。山地等もppバンド間のネスティングに伴う分極関数の増大が対形成に重要であると指摘した。山地等のモデルではppバンドのギャップの方がpsバンドのギャップより大きい。
トンネル分光で観測されている異常に小さなギャップや光電子分光や比熱測定から示唆されている複数のギャップと、バンド間で異なる大きさのギャップを予言するモデルとは関連がある可能性はあるが、実験的にモデルの正否を判断できる段階には未だ至っていないと考えられる。
高温超伝導の発見以来、超伝導ギャップの特徴を明らかにするための実験手法は、どれをとっても極めて洗練されたものとなってきている。これらの手法がMgB2に効果的に適用されれば、早い段階で超伝導発現機構は明らかになることは間違いないと考えられる。しかしながら、MgB2の場合、極めて短期間に膨大な実験が行われたにもかかわらず、その全ては多結晶体に対して行われたものであり、粒界、異方性等、試料に対する問題が常につきまとっている。良質単結晶の育成が急務である。これまで単結晶作製の報告は無いが、水面下ではいくつものプロジェクトが走っていることは想像に難くない。これらのプロジェクトが、衝突すること無しに、水面に緊急浮上することを期待したい。


写真2:左から銭谷・中川・永松・広中氏
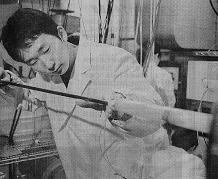
写真3:実験中の永松氏(日本経済新聞2001年4月4日夕刊より)
(レポーター:東京大学新領域創成科学研究科物質系助教授 花栗哲郎)